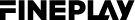こんにちは、Yohです。
今回は縁あってBOX LLCの共同創業者である阿部の連載「FINEPLAY INSIGHT」に寄稿させて頂くことになりました。
僕はBOX LLCの経営を通じてマーケティングやブランディングに関するコンサルティング活動を行う傍ら、自ら2018年に立ち上げたスタートアップでストリートプレイヤー向けの動画管理アプリ-PAARK-および映像作品販売マーケット-PAARK Market-を運営しています。
その中で、音楽著作権がカルチャーシーンに与えるインパクトについて考える機会が非常に多く、皆さんにもこの場を借りてお伝え出来ればと思い、今回のテーマを設定しました。少し難しい話も多くなるかもしれませんが、是非最後までお付き合い頂けると幸いです。
音楽著作権とは?
そもそも「音楽に関する著作権」とは何か、非常に曖昧な理解をしている方々も多いのかなと思います。音楽に関する著作権とは簡単にいうと、作曲家、作詞家、演奏家、歌手などの楽曲を制作するにあたって関与した人々に「これを作ったのは君たちだから、この楽曲を独占的に利用して良いよ」という権利のことです。だからこの楽曲を作った人たち(以下「著作者」といいます)以外の人が「この楽曲を使って踊ったり何かしたい!」という場合には、基本的には著作者に利用料を支払う必要があります。
しかし、楽曲を利用したい人がその都度著作者全員の許可を得るなり利用料を支払うことというのは、双方の手間を考えると現実的には不可能です。そのために存在する団体が、JASRACやその他の著作権管理団体です。「著作権プラットフォーム」というとわかりやすいでしょうか。JASRACを例にとると、音楽を利用したい人はJASRACにお金を支払うことで使いたい音楽を利用することが出来、著作者にはJASRACを通じてお金が支払われるという仕組みになっています。この仕組みのおかげで、しっかりと利用者から著作者に著作権料としてお金が流れる原理になっています。
ややこしいのが、著作隣接権
この著作権だけでも既に難しい話になってきていますが、それよりもさらにややこしいのが「著作隣接権」です。著作隣接権とは、音楽を作った著作者本人ではなく、例えば音楽をCDに録音して複製する機能を持つ音楽レーベルなど、音楽を世の中に伝えていくのに必要な役割を果たした人や会社に発生する権利です。音楽レーベルに所属しているアーティストが新曲をリリースする場合を例に考えると、アーティストの新曲を録音してマスターテープを制作し、それをディストリビュートする役割を担っている音楽レーベルには代表的な著作隣接権の一つである「原盤権」という権利が発生します。簡単にいうと「マスターテープを制作する」という業務を担った音楽レーベルに付与される権利なので、「その録音された音源」を利用しようとする楽曲利用者は、この原盤権を持つ音楽レーベルの許諾を取る必要があります。
この原盤権がストリートシーンにとっては実は非常にやっかいなんです。なぜなら、原盤権に関しては前述のJASRACのような管理団体が広くは存在しないからです。一部、NexToneなどの団体が音楽レーベルとの契約のもと原盤権を管理している例もありますが、基本的には音楽レーベルが原盤権を保有していることがほとんどです。すなわち、基本的にはいかにJASRACにお金を支払って著作権侵害をクリア出来ても、音楽レーベルの許諾を取らないと原盤権を侵害してしまうことになるので、楽曲を利用したいストリートシーン側からしてみると、その楽曲を使って踊ったり大会を催したりすることが出来ないのです。
ちなみに著作権および著作隣接権ともに、私的利用に関しては許諾が不要となっています。みなさんが自宅でCDを聞いたりしても怒られないのはそのためです。一方で、お客さんからお金をもらったうえでその音楽を演奏したり、歌ったり、その音楽で踊ったりする場合には全て著作権もしくは著作隣接権に関する許諾を得る必要があります。許諾を得ないでやってしまった場合には、権利侵害として権利保有者である著作権者もしくは音楽レーベルに訴えられる可能性が出てきてしまいます。
YouTubeで「歌ってみてみた」動画が投稿出来るのはなぜ?
ここで少し話が脱線しますが、YouTubeでシンガーや歌うまさんによって投稿された「歌ってみた」動画が削除されずにYouTube上で閲覧可能な状態で残っているのはなぜでしょうか。
それは、YouTubeがJASRACなどの著作権管理団体にお金を払っており、かつ、音楽レーベルとの提携を通じて構築した「Content ID」という楽曲データ管理システムで原盤権に関する管理を行なっているからです。すなわち基本的にはYouTubeでは著作権および原盤権の双方に関して、ユーザーが動画をあげても権利侵害が起きないような仕組みを作ってくれている、ということになります。
まず著作権に関して、YouTubeはJASRACやその他の著作権管理団体と著作権に関する包括契約を締結しており、ユーザーがJASRACの管理楽曲を使った動画をアップロードする場合は「YouTube側がお金を払ってくれることになってるので、ユーザーの動画アップロードは自由にやってもいいよ」ということになっています。そのためユーザーは自由にJASRACやその他管理団体の管理楽曲を利用した動画をアップロードすることが出来ます。
また原盤権に関しては、前述したYouTube独自のContent IDという楽曲データ管理システムに、主要な音楽レーベルが原盤権を保有する楽曲の多くが登録されており、原盤を使用した動画がYouTube上で何回再生されたかなどの情報もすべて管理されています。そのためYouTubeは原盤権を保有する音楽レーベルに対して、楽曲の再生回数や予め定められた契約条件に基づいて音楽レーベルに原盤権使用料を支払うことでユーザーが原盤権侵害を侵してしまうことがないようにしています。また原盤権保有者の中には、金銭を原盤権使用料としてもらうのではなく、YouTubeの動画を再生すると流れてくる広告の中から一部の広告料を受け取るという形で楽曲利用を許容しているケースも多々存在します。
著作権が起点でいまのダンスシーンにおきていること
さて、ここからいよいよストリートシーン、特にダンスの話に入っていきます。ここ1〜2年はコロナウイルスの影響もあり、ダンスバトルがオンラインで配信されることも多くなってきました。ブレイキンで言えばRed Bull BC Oneなど、大きな大会になればなるほど今やオンライン配信は当たり前と言えるのではないでしょうか。
オンライン配信は無料のものもありますが、会場で観客を入れて開催していたりスポンサー企業からの収入があったり、基本的にはビジネス目的(=大会運営を通じて金銭の実入りがある)で開催されているものがほとんどです。従って、前述の著作権および著作隣接権の問題が発生します。お金をもらって大会を開催している以上、音楽の私的利用には該当せず、しっかり著作権料や原盤権料を支払う必要があります。
そのため、音楽レーベルが原盤権を保有している楽曲は、基本的には権利者の許諾をとってお金を支払わないとダンスバトルで流すことが出来ません。つまり、ダンスバトルで「ダンサーのみんなが練習で使っているあの曲」のような有名楽曲をDJが流すためには、事前に著作権および原盤権の権利者に楽曲の利用許諾を取っておく必要がある、ということになります。
しかし、それは現在のダンスバトルの運営チームとしてはかなりハードルが高いことです。そもそも主要音楽レーベルのようなグローバル企業から小さな企業もしくは団体、場合によっては個人が許諾を得ること自体がかなり手間ですし、現実的にはほとんど不可能です。結果として、オンライン配信をしていたり集客をしている大きなダンスバトルであればあるほど「ダンサーのみんなが練習で使っているあの曲」をバトルの中で流すことが出来なくなっています。
そのため、ここ数年は「ダンサーのみんなが練習で使っているあの曲」ではなく、「トラックメーカーが(主催者に)提供してくれた楽曲」をダンスバトルで使うケースが増えています。トラックメーカーの中にはJASRACに著作権管理を委託していなかったり、音楽レーベルに所属していない方も多くいらっしゃいます。このような場合にはトラックメーカー自身が著作権および原盤権も保有している権利者ということになるので、トラックメーカー本人からの許諾さえ得られれば、権利侵害をすることなくダンスバトルで楽曲を利用できることになります。このこと自体はとても素晴らしいことで、トラックメーカーの楽曲が世界への配信でフックアップされる効果もあり、ストリートシーン全体にとってはとても良いことだと思います。
このように実務的な手続きの複雑さも考えると、「ダンサーのみんなが練習で使っているあの曲」は現実的に採用がほとんど不可能で、「トラックメーカーが提供してくれた楽曲」の利用がダンスバトルで増えざるを得ない状況を、みなさんもご理解いただけるのではないでしょうか。
ダンスバトルで流れる曲がダンスシーンに影響を与えている
では「ダンサーのみんなが練習で使っているあの曲」と「トラックメーカーが提供してくれた楽曲」をダンスバトルで使うことの違いは、どこにあるのでしょうか。これは捉え方は人によってそれぞれかと思いますが、個人的には「ダンサーのみんなが練習で使っているあの曲」は有名曲を中心に歌モノが多かったり、有名なラップバースが入っていたり、曲自体に色んなストーリーや文脈がある楽曲が多い一方、「トラックメーカーが提供してくれた楽曲」はインストやドラム中心のブレイクビーツが多く、演奏家やシンガーが参加したバンドサウンドやメロディアスな楽曲は少ない印象があります。
そのため、著作権や原盤権侵害を防ぐ必要がある大きなダンスバトルと、地元で仲間と突発的に沸き起こる権利侵害を意識する必要性がない(=私的、もしくは私的に限りなく近い)バトルで流れる曲は大きく方向性が異なり、結果として両者で「勝つ」ために必要なダンスが違ってきているのではないか、という仮説を個人的には持っています。
大きなダンスバトル:よりアスリート志向に
すでに述べたとおり、Red Bull BC Oneのような大きなダンスバトルでは、著作権や原盤権を考慮して一般的に知られた有名楽曲ではなく、トラックメーカーが制作した楽曲が中心に流れることになります。その結果、ストーリーやメロディアスな要素が多い楽曲を使用したバトルよりも、パフォーマンス要素の強い踊りでいかにミスなくムーブをかますか、というウェイトがジャッジの評価で高まるのかと思います。
そう考えると、大きなダンスバトルになればなるほど、ダンサー側の意識は大技の成功やミスしないことが重要になってくる一方、音楽に対する表現性が占めるウェイトは相対的に下がっていくように感じます。よりアスリート的なダンススタイルが求められていることは、著作権の観点からは必然だと思います。
小さなダンスバトル:よりカルチャー志向に
一方でローカルの小さなバトルなど、お金を取らずにやっているものもたくさんある現状を踏まえると、音楽著作権の侵害を(実務的に)意識する必要性が相対的に低くなります。結果として、流れる楽曲がいわゆる「ダンサーのみんなが練習で使っているあの曲」とか「ブレイキンといえばこの曲」みたいなものに寄っていきます。
このようなローカルやアンダーグラウンドのバトルでは、音楽性が占めるウェイトが相対的に上がってきます。楽曲が持っている時代的・人物的なバックグラウンド、過去にその楽曲を使って繰り広げられたバトルのストーリーなどに加えて、自分がどのような表現を乗せていくのか、というダンサー一人一人の生き方や価値観を踏まえた踊り方がとても重要になってくると個人的には思います。このようなシーンではアスリート的なダンススタイルだけでは物足りず、もっと幅広い一人一人の価値観や生き方、カルチャーに根ざしたスタイルがより価値を出してくると思います。
批評や対立ではなく、求められるのは相互理解
これは良し悪しの議論ではなく、現在のダンスシーンを音楽著作権の切り口から客観的にみた時に、二つの方向性が生まれてきているということだと思います。
大きなダンスバトルで「勝つ」ことを目的に据えると、そのための戦い方というものが見えてきます。これは2024年のパリ五輪を控えているブレイキンにとっても非常に重要なポイントだと思います。体操や柔道などの五輪競技と同じく、勝つための基本的な方程式があり、それを誰よりも高いレベルで実践するアスリートとして五輪の頂点を目指す。その中にも個人ごとに得意不得意があり個性があり、その個性を最大限活かしながら決められたルールの中で勝ちを目指す。日本のブレイキンシーンが現時点で五輪のメダルを狙える状況にあること自体が本当に素晴らしいですし、その背後にはJDSFを中心に尽力してきた方々の血の滲む努力と想いがあり、そこへのリスペクトをシーンに関わる誰もが持つべきだと思います。
一方で、小さな地元のバトルによって成り立っているシーンのことも同じ水準で大事にするべきです。元々音楽著作権や原盤権などは(実質的に)関係のない、ローカルのフリースタイルサイファーで成り立ってきた視点からいえば、ダンスと音楽は切り離すことが出来ないものです。その音楽自体が持っている歴史や、その音楽に乗せて繰り広げられてきたレジェンドたちによるダンスの歴史の上に、自分のアイデンティティを乗せていく。そうすることでダンスシーンを発展させていくという考え方もまた、絶対になくしてはならないものだと思います。
そもそも文化は画一的な成長の仕方をするのではなく、その時々の政治の思惑やシーンの向いている方向によって都度方向性を変えながら歴史を紡いできました。すなわち、その文化の最先端においては常に相対する考え方やスタイルがあるのが文化の宿命であり、それぞれをお互いにリスペクトして共存しているという状態こそが発展を支えているのではないか、と最近感じています。
繰り返しになりますが、僕はどちらが良くてどちらが悪いとは思いません。むしろ、その真逆です。当たり前のこととして色んなスタイルのダンサーがいて良いということと、その中でも音楽著作権がダンスシーンのバトルのあり方に影響を与えているという事実を皆で認識することで、異なる方向性であってもお互いをわかりあえる、より良いシーンに発展していくのではないか、と思っています。
BTSの事例から考えられる今後の音楽著作権の方向性
また少し話が脱線しますが、現在世界の音楽シーンを席巻しているBTS(防弾少年団)の所属事務所HYBE(ハイブ)は、ファンの音楽二次利用に関して比較的寛容な姿勢を取ることが多いことで知られています。特に韓国の音楽シーンで言えることなのですが、ファンがアーティストの楽曲を使って「踊ってみた」動画等を配信することが音楽サブスクリプションサービス上での再生回数やCDの売上枚数にプラスの影響をもたらすという考え方が主流になってきています。最近ではTikTokも音楽レーベル各社と提携契約を結びファンのTikTok上での音楽利用を正式に開放する動きが進んでいます。
僕個人としても、今後はこの流れが加速していくと考えています。そもそも音楽著作権は著作者の努力に報いることで文化の発展を促すことを目的としている権利なので、YouTubeやTikTokで消費者がUGC(User Generated Content)をアップロードして楽しむことが主流になっている昨今では、よりユーザーフレンドリーな立場で音楽著作権を捉える権利保有者が増えていくのではないかと思っています。
今後のシーンに対して思うこと
HYBEのような流れも踏まえると、今後はイベントの主催者が音楽著作権に関するスタンスを明確に打ち出すことが重要になってくると思います。例えば、ダンスバトルの主催者が音楽レーベルと包括的な業務提携を行うことによって「ダンサーのみんなが練習で使っているあの曲」をダンスバトルで利用出来るようにし、ストーリーやアンダーグラウンドのカルチャーに根ざしたスタイルのダンサーも、より大きなバトルで活躍出来るようになる方向性を打ち出すやり方も考えられると思います。
また、そうでなくとも、アスリート志向の強いダンスバトルからカルチャー志向の強いダンスバトルまで、イベントのコンセプトに幅広いグラデーションがある中で、イベントの主催者がバトルのコンセプトや目的、それに紐づいて流す音楽の方向性を明確に打ち出すことが大事だと思います。それによってダンサーが「勝つ」ための戦略を考えることも面白みですし、「色んな大会があって、色んな曲があって、色んなダンサーがいて、色んな勝ち方があって、それぞれ違うけどみんないいよね」という共存思考がシーン全体で高まるのではと思います。
今回は長々と、音楽著作権がストリートシーン、特にストリートダンスシーンに与えるインパクトについて個人的な考察を交えて述べさせていただきました。もちろん僕の考え方だけが正しいとは思っていませんし、シーン全体でも色んな意見があると思います。だからこそ、僕は色んな人と引き続きこのようなストリートシーンに関する建設的な議論を交わしていきたいと思っています。重要なことは、お互いがお互いの意見を理解し尊重したその先にカルチャーの発展があるということをみんなで理解しておくことだと思います。シーンに関わる全員がそれぞれの立場から考え、ストリートシーンの発展のためにかましていけたら本望です。
AUTHOR: 井本陽/ Yoh Imoto
幼少期をニューヨークで過ごしたことがきっかけで小学校時代からHIPHOPにのめり込む。中学時代からダンスを始め、その後DJ、ダブルダッチ、スケートボード、ビートメイキングと活動の幅を広げる。大学卒業後は会計事務所、証券会社を経て2013年戦略コンサルティングファーム ボストン・コンサルティング・グループに入社。2018年退社後ストリートカルチャー領域でストリートプレイヤー向けの動画管理アプリ-PAARK-および映像作品販売ウェブサービス-PAARK Market-を提供するスタートアップOne Dollar Bill Inc.を創業する傍ら、戦略ブティックBOX LLCを共同創業。
現在、One Dollar Bill Inc. 代表およびBOX LLC Co-founderを兼任。東京大学経済学部卒。
SPECIAL EDITION

FINEPLAYはアクションスポーツ・ストリートカルチャーに特化した総合ニュースメディアです。2013年9月より運営を開始し、世界中のサーフィン、ダンス、ウェイクボード、スケートボード、スノーボード、クライミング、パルクール、フリースタイルなどストリート・アクションスポーツを中心としたアスリート・プロダクト・イベント・カルチャー情報を提供しています。
アクションスポーツ・ストリートカルチャーの映像コンテンツやニュースを通して、ストリート・アクションスポーツの魅力を沢山の人へ伝えていきます。
●今日 ○イベント開催日
-
skate10歳のスケートボーダー・河上恵蒔、X Gamesで男子史上最年少で銅メダルを獲得!2025.06.2910歳のスケートボーダー・河上恵蒔(かわかみ・えま サカイサイクル所属)が、日本時間6月28日にアメリカのソルトレイクシティで開催された「X Games Salt Lake City 2025」で、男子史上最年少となる10歳9ヶ月でブロンズメダルを獲得した。河上は昨年米国で行われた「X Games Ventura 2024」に9歳9ヶ月で初出場し、男子最年少出場記録を更新。さらに3つのギネス世界記録を樹立し、一躍世界の注目を集めた。 Photo: ©︎X Games 今大会の決勝では、1本目で頭部に強い衝撃を受ける心配な場面もあったが、その後の演技に気合を注入。2本目では得意の“900”(2回転半)を含む複数の高難度トリックを成功させ、高得点をマークした。3本目には世界初の連続トリックとして、900を2度連続でメイクした直後に720(2回転)を成功させ、観客を沸かせた。表彰式後、河上は「X Gamesでメダルを獲ることがずっと夢だったので、本当にうれしいです」と満面の笑み。そして、「ギー・クーリ選手の最年少メダル獲得記録を更新できてとても嬉しいです!」と喜びを語った。 大会結果 Photo: ©︎X Games 1位 Gui Khury (ギー・クーリ)ブラジル2位 JD Sanchez(ジェイディー・サンチェス)アメリカ3位 河上 恵蒔(カワカミ・エマ)日本
-
fmx関西初上陸のX Gamesを盛り上げたのは大迫力なパフォーマンスと様々なサイドコンテンツ【X Games Osaka 2025】Moto X & 豪華コンテンツまとめレポート2025.06.26関西初上陸となり2025年6月20日(金)~22日(日)に京セラドーム大阪で開催され、数日経った今もまだまだ大会の熱が冷めあらぬ、その余韻が残る世界最大のアクションスポーツの祭典「X Games Osaka 2025」。いまだにSNS上ではX Games Osakaの投稿が尽きず、いかに鮮明にこのイベントがアクションスポーツファンの目に映ったかが感じられている。 そしてBMXとスケートボードに並び、このX Gamesを盛り上げる立役者になっているのが「Moto X(フリースタイルモトクロス)」。大会初日には競技としてベストトリック種目が、最終日にはデモンストレーションとしてライダーたちの息をのむ豪快なライディングが披露されて「X Games Osaka 2025」を二日間にわたり大会を最高潮に盛り上げて締め括った。 また今回は各競技による世界最高峰の戦いはもちろんのこと、イベントをさらに盛り上げる様々な豪華音楽ライブやBMX・スケートボード体験会なども行われ、フードトラックやオフィシャルバーなども設置されては五感で来場者を楽しませた。 本記事では今大会の花形種目として会場を盛り上げたMoto Xのメダリストのライディングと、連日イベントを盛り上げた豪華コンテンツをまとめて紹介。 X Games Osaka 2025にて初の屋内開催となった「Moto X・ベストトリック」はロブ・アデルバーグが2大会連続の金メダルを獲得! ロブ・アデルバーグ ©︎Hikaru Funyu/X Games 前回の「X Games Chiba 2024」とは異なり、屋内での競技開催となった今回の「Moto X・ベストトリック」は天候の影響を受けない上にドームという会場ということもあり、バイクのエンジン音と豪快なジャンプが会場に映えて、より観客のボルテージを最高潮に引き上げた。 今大会の競技フォーマットは2本のトライのうちのベストスコア採用方式で争われ、5名の招待選手が出場。そのスタートリストはベニー・リチャーズ(オーストラリア)、渡辺元樹、東野貴行、ロブ・アデルバーグ(オーストラリア)、ジャクソン・ストロング(オーストラリア)となり、今回はどんな世界最高峰のトリックが飛び出してくるのかが注目の一戦となった。 以下は入賞者3名が魅せたベストトリックを紹介。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) まずは今回金メダルを獲得した本種目X Games最多メダリストのロブ・アデルバーグ(オーストラリア)の「ロウドヴァ・フロントフリップ」を紹介。このトリックはトリックを前方に1回転する「フロントフリップ」をしながら、サドルを掴みながら足をハンドルに引っ掛けて仰け反る「ロウドヴァ」で行うという超大技。もちろん前回転するため、前方に投げ出されるような遠心力に耐えながらもバイク上で仰け反るという超高難度のこのトリックを大会初メイクし、92.66ptをマークすると自身9個目のX Games金メダルを獲得して通算19個目のメダルを記録した。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) 本種目で銀メダルを獲得したのはベニー・リチャーズ(オーストラリア)。彼がメイクしたのは「スペシャルフリップ」というバイク上で「ボディバリアル」をするトリック。バイクの上で自分自身が後方一回転して戻るというこの高難度トリックを決めたFMX界では24歳という若手の彼が見せたパワフルでクリーンなライディングに会場は大盛り上がりだった。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) そして今回X Games銅メダルを獲得したのは、長年FMX業界を牽引するレジェンドライダーであるジャクソン・ストロング(オーストラリア)。彼がメイクしたのは「フロントフリップ・シートグラブインディエアー」という前方に1回転する「フロントフリップ」の中で両手を離してサドルを掴み、足をクロスして投げ出す「シートグラブインディエアー」のコンボトリック。ストロングのスタイルが溢れた豪快なトリックに会場は歓声と共に盛り上がっていた。 大会結果 左からリチャーズ、アデルバーグ、ストロングの順©︎Jason Halayko / X Games 優勝 ロブ・アデルバーグ(オーストラリア)/ 92.66pt準優勝 ベニー・リチャーズ(オーストラリア)/ 91.00pt3位 ジャクソン・ストロング(オーストラリア)/ 90.00pt4位 東野 貴行(日本)/ 86.66pt5位 渡辺 元樹(日本)/ 83.66pt 関西初開催となったX Games Osaka 2025のボルテージを最高潮に引き上げたのは豪華サイドコンテンツの数々。 「X Games Osaka 2025」では豪華なサイドコンテンツの数々が会場をさらに盛り上げた。その中でも今回はショーケース「豪華音楽ライブ」、そして「スケートボード・BMX無料体験会」そして連日来場者のお腹を満たし喉を潤した「フードトラック」や「オフィシャルバー」の様子を紹介。 人気アイドルグループ「IMP.」や「DXTEEN」、そしてビートボックスグループ「SARUKANI」による豪華音楽ライブ SARUKANI ©︎X Games Japan 「X Games Osaka 2025」の会場をさらにヒートアップさせたのは、競技だけじゃない。スケートやBMXの熱戦が繰り広げられる傍ら、特設ステージでは人気アイドルグループ「IMP.」や「DXTEEN」、そして世界を舞台に活躍するビートボックスグループ「SARUKANI」によるスペシャルライブが行われ、観客を熱狂の渦に包み込んだ。 初日にパフォーマンスを行ったIMP.は、キレのあるダンスと力強い歌声で一気に会場のボルテージを上昇させ、人気曲を含むセットリストでファンのみならず、会場のアクションスポーツ好きな観客も魅了。 最終日に現れたのは世界レベルのビートボックスグループSARUKANI。4人の声だけで繰り広げられる圧巻のサウンドとパフォーマンスに、観客からは歓声が止まらなかった。複雑なビートとダイナミックな展開で、スポーツ観戦とはまた違った種類の“アドレナリン”を届けてくれた。 そしてラストを飾ったのはDXTEEN。韓国を拠点に活動する彼らはスタイリッシュかつ見事な歌声で多くの観客の心を掴み、彼らならではの爽やかで多彩な魅力を存分に発揮した。X Gamesならではの“スポーツ×音楽”のクロスカルチャー。世界トップレベルのライディングと同じ空間で、今をときめくアーティストたちがエネルギーをぶつけ合った、まさに特別な夜だった。 誰でも参加OK!未来のスターが集う、スケートボード・BMX無料体験会 ©︎Miku Sakamoto / X Games Japan 「X Games Osaka 2025」の熱狂が渦巻く京セラドーム大阪のコースサイドに用意された特設エリアでは、スケートボードとBMXの無料体験会が開催され、多くの親子連れや初心者でにぎわいを見せた。 特設のフラットスペースでは、インストラクターによるレクチャーのもと、初めてボードやBMXに乗る子どもたちが楽しそうに挑戦。ヘルメットやプロテクターも無料で貸し出され、安全面にも配慮された内容となっており、誰でも安心してアクションスポーツの世界に触れられる機会となった。 会場ではミニゲームやオーリーコンテストも随時実施され、みんなで楽しめる場面も。体験することで競技への理解が深まり、観戦の楽しみ方も一層広がるイベントとなった。競技観戦だけではない、触れて、感じて、楽しめる。X Gamesならではのアクションスポーツカルチャーの裾野を広げるこの試みは、未来のスターたちの第一歩をそっと後押ししていた。 ©︎Miku Sakamoto / X Games Japan 観戦の合間にひと息。多彩なフードコーナーでお腹も心も満たされる! ©︎X Games Japan 京セラドーム大阪のアリーナ内に設けられたフードコーナーは、世界トップレベルのライディングに負けないほどの熱気と行列でにぎわっていた。 会場には、モスバーガーをはじめとしたストリートフードをはじめ、大阪名物のたこ焼きやラーメンなどの地元グルメも勢揃い。国際色とローカル感が融合したX Games流の屋台村が出現したかのような雰囲気となった。 ©︎Miku Sakamoto / X Games Japan また暑い日にピッタリなキンキンに冷えたビールやハイボールなどのお酒をはじめ、コーラやスポーツドリンクなど喉を潤すドリンクを提供する「オフィシャルバー」も用意。 競技観戦の合間に、気軽に立ち寄ってエネルギーをチャージ。お腹を満たすだけでなく、フードやドリンクからもX Gamesのカルチャーを味わえる。そんな空間が広がっていた。 最後に ©︎Miku Sakamoto / X Games Japan 歓声、拍手、そして笑顔。京セラドームを舞台に繰り広げられた「X Games Osaka 2025」は、アクションスポーツの熱狂と、カルチャーの豊かさが溶け合う特別な3日間となった。 世界トップレベルのライダーたちが見せた技の数々は、観る者に勇気と驚きを与えてくれた。スケートボード、BMX、Moto X、どの競技にも、それぞれのドラマと感動があった。 さらに、豪華アーティストによるライブパフォーマンス、地元の味を楽しめるフードエリア、子どもたちが初めてスケートに挑戦する体験会など、会場全体がひとつの大きなフェスティバルとして調和していた。 スポーツと音楽、食、体験がつながり、生まれたたくさんの感動。このイベントがきっかけとなり、新たな夢を抱いた誰かが、きっと未来のX Gamesの舞台に立つ日が来ることを期待したい。今後もX Games Japanの動向に目が離せない。 大会概要 ⼤会名称 : X Games Osaka 2025開催期間 : 2025年6月20日(金)~22日(日) – 3日間 (一般開場は21~22日の2日間)-※詳細は公式HPをご覧ください。※金曜は公式練習日のため関係者・招待客・取材媒体のみ。一般入場は土曜と日曜の2日間です。 会場:京セラドーム大阪(KYOCERA DOME OSAKA) 主催: X Games Osaka 2025 組織委員会、株式会社 XGJ、日本テレビ放送網株式会社、株式会社ライブエグザム、株式会社イープラス、株式会社CB、株式会社グッドスマイルカンパニー、読売テレビ放送株式会社 主管: 大阪府、大阪市 後援: 一般社団法人ワールドスケートジャパン、一般社団法人日本スケートボーディング連盟、一般社団法人全日本フリースタイルBMX連盟、一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会、一般社団法人TEAM JAPAN MX PROJECT、FM802 / FM COCOLO、読売新聞社 協賛: Monster Energy、INSTYLE GROUP、ムラサキスポーツ、モスフードサービス、日本郵政、SANDISK、バンテリン、Mizkan NEW酢SHOT 協力: 公益財団法人JKA、モトクロスインターナショナル、株式会社JTB、シミズオクト、Skatelite by 井上スダレ株式会社、Yogibo、TOYO TIRE株式会社、TryHard JAPAN、くれおーる、ラーメンまこと屋
-
skateX Games史に刻まれる快挙がいくつも生まれた大会【X Games Osaka 2025】スケートボード各種目まとめレポート2025.06.25今年、大阪万博で世界から注目と多くの観光客が集まっているここ大阪で、日本では4回目のX Gamesとなった「X Games Osaka 2025」が京セラドーム大阪にて2025年6月20日(金)~22日(日)に開催され、スケートボード競技からは「パーク」、「ストリート」、「バート」、「バート・ベストトリック」の4種目が行われた。なおスケートボード競技における日本人最高位として男子ストリートで根附海龍選手が自身初のX Games金メダルを獲得した。世界最高レベルの選手たちを大勢有し、今では世界からスケートボード最強国と知られる日本から、今大会にはオリンピックや世界大会で結果を残すトップ選手たちが出場。同じく世界最高峰の豪華海外招待選手たちを相手にX Gamesの歴史に新たな1ページを刻む快挙も生まれるほど熾烈な戦いが繰り広げられた。 「X Games Osaka 2025」の会場は大阪市の中心地にある京セラドーム大阪。交通の利便性も相まって関西地域の各方面からのアクセスも良く、会場内は屋内で天候に左右されず、かつ今回のコースもスタンドとアリーナ共に観戦しやすい配置となったことから観客は今まで以上に臨場感を感じながら、目の前で繰り広げられる世界最高峰のトップアスリートのパフォーマンスを観戦。その熱気は大きな会場を包み込み終始大盛り上がりであった。 そして毎年注目集まるのが、日本らしさが詰まったオリジナリティあふれるコースレイアウト。パークコースでは都会のど真ん中をイメージしたコースに様々なセクションの数々が、そしてストリートコースでは大阪の人気観光地の「道頓堀」をモチーフにしたコースの中に大小様々なセクションが設置された。この普段の国際大会とはコースの形状も雰囲気も異なるX Gamesならではの環境下、いつもより短い練習時間の中で自分たちのライディングをプラクティスでまとめる技術も求められた。 本記事では各種目の入賞者にフォーカスした大会レポートとしてご紹介。 ストリート種目は根附海龍が昨年のリベンジを果たし、自身初X Games金メダルを獲得! 男子ストリートで金メダルを獲得した根附海龍©Jason Halayko/X Games 女子ストリート クロエ・コベル ©Jason Halayko/X Games 大会初日に行われた女子ストリートは、優勝候補の一角であった赤間凛音が怪我のリハビリ中のため出場を見送ったことでリザーバーの松本雪聖が出場を決め、吉沢恋、中山楓奈、織田夢海、伊藤美優、西矢椛の日本人選手勢6名に加えて、アメリカ合衆国のペイジ・ハイン、そしてオーストラリアの英雄クロエ・コベルの8名により争われた。X Gamesの新フォーマットであるプレイオフを勝ち上がった4名が決勝で争う形になり、決勝へ勝ち上がったのはクロエ・コベル、伊藤美優、吉沢恋、松本雪聖。プレイオフと同様に決勝でも45秒間のランを2本走行し、その中で最も良い得点のランが採用されるベストランフォーマットでの戦いとなった。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) まず、スピードあるライディングの中に様々なトリックを軽々とメイクしてきた弱冠13歳の松本雪聖はレールでの「キックフリップフロントサイドボードスライド」やクオーターでの「ブラント to フェイキー」、さらには「ハーフキャブフロントサイド180」などを次々とメイク。ラストは「キックフリップバックサイドリップスライド」までフルメイクしラン1本目で77.00ptをマーク。そのまま3位の座を守り切り今回は見事銅メダルを獲得した。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) 「X Games Ventura 2024」にて初出場で初のX Games 女王に輝き、昨年の「X Games Chiba 2024」で銀メダルを獲得している伊藤美優はハンドレールでの「フロントサイドフィーブルグラインド」でランをスタートすると、クオーターパイプでの「バックサイドブラント」や、彼女の代名詞トリックの一つでもある「ハードフリップ」を決めるなど安定したライディングの中に見られるパワーとフローを合わせたラインで1本目からフルメイク。2本目以降ではスコアアップできず銀メダルとなったものの、これで今まで出場してきたX Gamesでは全てメダルを獲得しているという功績を示した。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) いつも練習からいち早くパークの特性を把握して、自身のラインを完成させている様子がうかがえるオーストラリアのクロエ・コベルは、まずX Gamesサインで「バックサイドクルックドグラインド」を決めてランをスタートすると、ヒップ越えの「ヒールフリップ」や、約11メートルにもおよぶ透明なプレキシグラスルーフセクション上で繰り出した「キックフリップ・マニュアル」で会場を沸かせる。ラストトリックでは波状のセクションから飛び出してレールでの「バックサイドリップスライド」も決め切りフルメイク。唯一の90点台をマークして見事金メダルに輝いた。なお今回でコベルは昨年の「X Games Chiba 2024」続いて優勝し自身3個目の金メダルを記録し、全体では6個目のX Gamesメダル獲得となった。 男子ストリート 根附海龍 ©Jason Halayko/X Games 計12名と今大会では一番出場者数多かった男子ストリートは、X Gamesの新フォーマットであるプレイオフを勝ち上がった6名が決勝で争う形に。プレイオフと同様に決勝でも45秒間のランを2本走行し、その中で最も良い得点のランが採用されるベストランフォーマットでの戦いとなった。今回は昨年の「X Games Chiba 2024」の覇者である白井空良が以前から痛めていた関節の大事をとって欠場となりオーストラリアのキーラン・ウーリーが急遽パーク種目とのダブルエントリー。日本人勢からは根附海龍、小野寺吟雲、佐々木音憧、池慧野巨、池田大暉の5名が出場となった。なおプレイオフを終えて決勝に進出したのは根附海龍、小野寺吟雲、佐々木音憧、韓国のジュニ・カン、アメリカ合衆国のジェイク・イラーディとジュリアン・アギラルディの6名に。 入賞メンバーはまずラン2本目でフルメイクを決めた小野寺吟雲が銅メダルを獲得。ハンドレールでの「キックフリップバックサイドテールスライドショービットアウト」でランをスタートすると、フラットバーでの「キックフリップフロントサイドブラントスライドビックスピンアウト」などをメイク。ラストトリックでは「ビックフリップフロントサイドボードスライドビッグスピンアウト」を決め切りフルメイクで90.66ptをマークした。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) そして今回終始見事なパフォーマンスを見せて銀メダルを獲得したのは韓国のジュニ・カン。現在16歳のカンは世界最高レベルのアマチュアの大会「Tampa Am」で優勝し世界から注目を集めているライダー。特筆すべきは彼のスタイルで2大会オリンピック金メダリストの堀米雄斗を彷彿とさせるトリックセレクション。決勝では2本目でスコアを伸ばしてきたのだが、ハンドレールでの「スイッチフロントサイド270バックサイドリップスライド」、「ノーリーヒールフリップ」、ギャップからの「バックサイドノーズブラントスライド」、ラストトリックには堀米の名前がつく「ノーリー270ノーズスライドバックサイド270アウト(通称:ユウトルネード)」を決め切りフルメイクで終えると91.66ptというハイスコアをマーク。今回韓国人スケーターとして初のX Games出場かつ初のX Gamesメダリストという快挙を収めた。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) そして今回並いる強豪たちを抑えて念願の金メダルを獲得したのが根附海龍。昨年の「X Games Chiba 2024」では最後の最後で逆転を許し銀メダルに終わっていた彼。今回でのリベンジを胸に挑んだ決勝では1本目から見事なランを見せる。ハンドレールでの「ヒールフリップバックサイドリップスライド」を皮切りにランを始めると、クオーターでの「キャバレリアルヒールフリップ」、ボックス越えの「レイトバックサイドビッグスピン」を決める。ラストトリックにはハンドレールでの「ヒールフリップバックサイドテールスライドビッグスピンアウト」を決めてフルメイク。スタイルとレベルの高さがミックスされたランに92.33ptがスコアされて暫定で首位に立ち、その後もその座を守り切り去年の雪辱を晴らす結果を見せた。 バート種目は女子カテゴリーが日本初開催!そして男子はブラジルのギー・クーリーが昨年に続き2冠達成! 「X Games」の花形種目とも言えるほど、ストリート種目やパーク種目と同様に日本人選手たちが大活躍を見せているバート種目。今大会ではついに日本初の女子カテゴリーも開催されて男子カテゴリーと共に世界最高峰のトリックの数々が観客たちを大いに沸かした。その中には新技も飛び出し、また世界のバート種目のレベルを引き上げた大会となった。 女子バート アリサ・トルー ©Jason Halayko/X Games 大会初日の一番最初の種目となった女子バートは、優勝候補のスカイ・ブラウン(イギリス)が欠場したことからリザーバーの松岡樹ノが出場を決め、日本人選手勢は貝原あさひと長谷川瑞穂の3名に加えて、オーストラリアのアリサ・トルーとミア・クレッツァー、リリー・ストファシウス(ドイツ)、リース・ネルソン(カナダ)、ライカ・ベンチュラ(ブラジル)の8名により争われた。 X Gamesの新フォーマットであるプレイオフを勝ち上がった4名が決勝で争う形になり、決勝へ勝ち上がったのはアリサ・トルー、貝原あさひ、ミア・クレッツァー、松岡樹ノ。プレイオフと同様に決勝でも30秒間のランを2本走行し、その中で最も良い得点のランが採用されるベストランフォーマットでの戦いとなった。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) 日本初開催の女子バートが行われた「X Games Osaka 2025」で銅メダルを獲得した日本の松岡樹ノ。今回リザーバーで急遽出場が決まった彼女だが、実は前日のプラクティスで転倒し肩を脱臼していたが、大会救護班の迅速な対応もあり大会出場が叶った。決勝まで勝ち上がった彼女は2本目でベストランを披露。ハイエアーから繰り出される「540」や「キックフリップインディグラブ」、「アリウープバリアルキックフリップインディグラブ」、「マドンナ」そしてラストトリックには「ロックンロールスライド」をメイクして77.66ptをマーク。そのままスコアを守り切り銅メダルを2大会連続で獲得した。まだ14歳の若手ライダーの彼女。今後の活躍に期待したい。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) 今回、女子バートで日本人最高位をマークしたのは貝原あさひ。昨年の「X Games Ventura 2024」にて銅メダルを獲得した彼女は、ラン2本目で素晴らしいライディングを見せた。「ボディバリアルベニハナ」を皮切りにランをスタートすると、彼女の得意技である「マドンナ」や「キックフリップインディグラブバックサイドエアー」、コーピングでの「フロントサイドノーズグラインド to リップスライド」そしてラストトリックには「フェイキーバリアルステールフィッシュグラブ」を決め切り79.00ptをマーク。前回大会の銅メダルを塗り替える銀メダルを獲得した。長い手足が映えるライディングがスタイリッシュな彼女の今後のさらなる活躍にも期待したい。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) 今回見事金メダルを獲得したのは近年負けなしの強さを見せるアリサ・トルー(オーストラリア)。今回も1本目から高難度なトリックでまとめたランを見せて圧勝。ベストスコアを残した2本目はウィニングランで迎える形となった。そのランでは30秒という限られた時間にも関わらず「バックサイド540」、「インディ360」、「スイッチマックツイスト」、そして「ハーフキャブフロントサイドノーズスライド」をメイクしアップデートするとさらにスコアを87.66ptまで伸ばし金メダルを獲得した。翌日のパーク種目を控えるこの時点で自身6個目のX Games金メダルを獲得する快挙となった。 男子バート ギー・クーリー ©Jason Halayko/X Games 同じく大会初日に開催された男子バートは、優勝候補のギー・クーリー(ブラジル)やエリオット・スローン(アメリカ合衆国)などを相手に、日本人選手勢は芝田モトと猪又湊哉、そして最年少出場選手の河上恵蒔の3名が出場。加えてアメリカ合衆国からJD・サンチェス、テイト・カリュー、トム・シャーが出場して計8名により争われた。 女子カテゴリー同様に、X Gamesの新フォーマットであるプレイオフを勝ち上がった4名が決勝で争う形になり、決勝へ勝ち上がったのはギー・クーリー、JD・サンチェス、トム・シャー、猪又湊哉。プレイオフと同様に決勝でも30秒間のランを2本走行し、その中で最も良い得点のランが採用されるベストランフォーマットでの戦いとなった。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) まず今回銅メダルを獲得したのはアメリカ合衆国のトム・シャー。数々の世界大会で結果を残しているトップライダーである彼は、大きな身体を活かしたパワフルで滞空時間の長いハイエアーの中で繰り出される高難度トリックが特徴的。決勝では1本目でベストランを披露。「フェイキーテールグラブ720」を皮切りに「アリーウープヒールフリップインディグラブ」、「キックフリップボディバリアル540」などをメイク。そして1本目と2本目共にラストトリックには「ブラントキックフリップフェイキー」をトライするも失敗しフルメイクとはならなかったが、1本目でマークした83.00ptを守り切り表彰台の座を獲得した。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) 今大会では新世代として強さを見せたのはアメリカ合衆国の16歳、JD・サンチェス。プラクティスの時点から好調な様子を見せていた彼。幅広いトリックセレクションの中からひとつひとつのトリックを高い精度を繰り出した彼は、ラン2本目で素晴らしいライディングを見せた。「フロントサイド360 to フェイキー」を皮切りに、常に高いエアーを保ちながら「キックフリップステイルフィッシュグラブ」や「フロントサイドヒールフリップボディバリアル360」そして「インディグラブ720」を綺麗に決め切るフルメイクランで88.33ptをマーク。1本目のスコアをアップデートし順位をジャンプアップ。自身初のX Gamesメダルを銀メダルとした。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) 今回唯一の90点台をマークし盤石な強さを見せたのはギー・クーリー(ブラジル)。1本目から見事なフルメイクで強さを見せると周りのライダーにプレッシャーをかけた。その1本目で見せたのは「900」、「ボディバリアル・キックフリップ540」、「ステイルフィッシュグラブ540」、「キックフリップ・インディグラブ540」、「キックフリップ・インディグラブ・トゥ・フェイキー」、そして「インディグラブ720:といった高難度の技を次々と成功させて、ランを終えるとスコアを90.66ptをマークして自身6個目のX Games金メダルを獲得した。 男子バート・ベストトリック ギー・クーリー ©Jason Halayko/X Games 大会最終日に行われたバート・ベストトリックでは20分間のジャムセッションの中で異次元のトリックが飛び出した。今大会では世界初メイクのトリックも披露されるなど、バートの競技レベルがさらに引き上げられた戦いが繰り広げられた。またなんと今回の表彰台の面々は偶然にも「X Games Chiba 2024」と同じメンバーとなった。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) 昨年の「X Games Chiba 2024」と同様に今回銅メダルを獲得したのは猪又湊哉。彼の最終トライで決め切って見せたのは「バックサイドバリアル540 to ハンドバリアルステイルフィッシュグラブ」だ。このトリックは世界初のトリックで彼自身が「雷神(RAIZIN)」と名付けた新しいシグネチャートリック。今大会ではランディングが少しブレてしまったことで銅メダルに止まったが完璧に決めきれば金メダルも狙えるトリックであることは間違いないだろう。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) そして前回同様に銀メダルを獲得したのは芝田モト。彼が3度目のトライでメイクしたのは前回の「X Games Chiba 2024」でもメイクした「フロントフットインポッシブルリーンエアー540」。もちろんこのトリックだけでも異次元の難しさを誇るのだが、実は他にも出したいトリックがあったという。今後彼がどんなトリックを繰り出すのかに注目だ。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) そんな異次元の高難度トリックバトルを制し、金メダルを獲得したのはギー・クーリー。昨年の「X Games Chiba 2024」にて時間ギリギリにメイクした「キックフリップボディバリアル900」を一発に決めて見せた。さらに完成度を上げたこのトリックは今回のベストトリックとなった。そしてクーリーはこれで2年連続でバートとバート・ベストトリックの2冠を達成し、彼の金メダル数は通算7個となった。また次のX Gamesではどんな歴史が生まれるのかにも期待したい。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) そして今回メダルは逃したものの触れておきたいのは河上恵蒔のライディング。河上は関西出身ということもあり大会前から多くの注目を集め、大会では結果としてはメダルに一歩届かず5位にとどまるも「1080」を決めてみせた。まだ弱冠10歳ながら世界を驚かせ続けている彼。今週末の「X Games Salt Lake City 2025」にも出場予定の彼だが今後の大会でどんなライディングをするのか注目だ。 パーク種目はアリサ・トルーが女子スケーター最多金メダル記録を更新!日本の四十住さくらが3年ぶりの銀メダル獲得 アリサ・トルー ©Jason Halayko/X Games 女子パーク 女子パークは大会最終日に開催され、優勝候補のアリサ・トルー(オーストラリア)やスカイ・ブラウン(イギリス)を相手に日本人選手勢からは開心那、四十住さくら、草木ひなの、藤井雪凛の4名が出場。さらにアメリカ合衆国のブライス・ウェットスタインとリリー・エリックソンを加えた計8名により争われた。 X Gamesの新フォーマットであるプレイオフを勝ち上がった4名が決勝で争う形になり、決勝へ勝ち上がったのはアリサ・トルー、開心那、四十住さくら、草木ひなのの4名。プレイオフと同様に決勝でも45秒間のランを2本走行した上で、最も良い得点のランが採用されるベストランフォーマットでの戦いとなった。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) 今大会で銅メダルを獲得したのは草木ひなの。今回の彼女のベストランは1本目で、ボックスジャンプで「サランラップ」をメイクしてランをスタートさせると、「バックサイド540」やコーピングでの「バックサイドロックンロールスライド」を綺麗にこなしながら、ボックスジャンプで「サランラップ360」をメイク。ラストトリックにはウォールセクションに「バックサイドボーンレス」を当て込みランを終えると85.66ptをマーク。そのスコアを最後まで守り切り見事銅メダルを獲得した。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) そして今回の3年ぶりのX Gamesメダルを獲得した四十住さくらは、2本目でランをアップデート。ボックスジャンプでの「バックサイドエアー」を皮切りにランをスタートし、「ヒールフリップインディグラブ」やコーピングでの「フロントサイドリップスライド」、そして昨年の「X Games Chiba 2024」ではメイクできなかったトランスファーでの「ノーグラブバックサイド540オーリー」を決め、ラストトリックを「バックサイドディザスターリバート」で締めてフルメイクでランを終えた。このランには87.66ptがスコアされ2位まで浮上。銀メダル獲得が決まった瞬間喜びの涙が浮かぶ様子も見られ、過去のX Gamesを含めて今までどれだけ努力をしてきたかを感じられた瞬間だった。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) そして今回見事金メダルを獲得したのは、昨年の「X Games Chiba 2024」の覇者でパリオリンピックでも金メダルを獲得するなどパーク種目においてもほぼ負けなしのアリサ・トルー(オーストラリア)。ラン2本目ではよりスピードとパワーをプラスしたランへアップデート。彼女の得意技の「マックツイスト」をはじめ「キックフリップインディグラブ」や「フロントサイドキャバレリアルステイルフィッシュグラブ」などを決め、ラストトリックには「スイッチマックツイスト」を決め切りフルメイクで終えるとトップの座を獲得した。なおこの結果から通算7個目となる金メダルを獲得し、レティシア・ブフォーニが保持していた「女子スケーター最多金メダル記録」を更新。しかもバート種目と2種目での2冠は3大会連続の快挙!どこまでこの記録を伸ばし続けるのか目が離せない。 男子パーク トム・シャー ©Yoshio Yoshida/X Games 男子パークは今大会の最終競技として開催され、日本人選手勢からは永原悠路が出場。海外招待選手としてトム・シャー(アメリカ合衆国)、キーガン・パルマー(オーストラリア)、テイト・カリュー(アメリカ合衆国)、ペドロ・バロス(ブラジル)、ギャビン・ボドガー(アメリカ合衆国)、キーラン・ウーリー(オーストラリア)、トレイ・ウッド(アメリカ合衆国)といった世界トップクラスのライダーたちを加えた計8名により争われた。 他の種目と同様にX Gamesの新フォーマットであるプレイオフを勝ち上がった4名が決勝で争う形になり、決勝へ勝ち上がったのはトム・シャー、キーガン・パルマー、ペドロ・バロス、テイト・カリューの4名。こちらもプレイオフと同様に決勝でも45秒間のランを2本走行した上で、最も良い得点のランが採用されるベストランフォーマットでの戦いとなった。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) まずは様々なフリップトリックをコンビネーションを中心にランを構成したテイト・カリュー(アメリカ合衆国)。今回は豪快な「キックフリップインディグラブ」や、コーピング周りでの流す「バックサイドスミスグラインド」や、「バックサイド540」、そしてディープエンドからX Gamesサインに当て込む「オーリーtoテール」など高難度かつスタイリッシュなランで84.00ptをマークし銅メダルを獲得した。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) 次にカリューを上回ったライディングを見せたのは2大会オリンピック金メダリストであるオーストラリアのキーガン・パルマー。コースを広く満遍なく使いながらライディングする彼は、クオーターでの「メロングラブ540」や「キックフリップアリーウープリーンエアー」、ボックスジャンプでの「リーンエアー360」、トランジションには「バックサイドテールスライド」を上手く使い加速。ラストトリックには「キックフリップインディグラブフェイキー」を決めきり見事銀メダルを獲得した。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) そんな二人を上回ったのは昨年の「X Games Chiba 2024」と同様に今大会のバートでも銅メダルを獲得したトム・シャー(アメリカ合衆国)がパーク種目でも金メダルを獲得。彼はバートで培われたハイエアーとトランジションでの見事な安定感が特徴的で、ベストランでは「テールグラブ540」や、ボルケーノでの「フロントブラント」、クオーターでの「アリーウープキックフリップインディグラブ」や、ボックスジャンプでの「ステイルフィッシュ360」、またディープエンドからX Gamesサインに当て込む「ノーズストール」、ラストトリックでは「フェイキー5-0」など幅広いトリックコンビネーションをフルメイクし2大会連続の金メダルを獲得。自身16個目のX Gamesメダルを持ち帰った。 大会結果 左から貝原、トルー、松岡の順 ©Jason Halayko/X Games 女子バート優勝 アリサ・トルー(オーストラリア)/ 87.66pt準優勝 貝原 あさひ(日本)/ 79.00pt3位 松岡 樹ノ(日本)/ 77.66pt4位 ミア・クレッツァー(オーストラリア)/ 52.66pt5位 長谷川 瑞穂(日本)6位 リリー・ストファシウス(ドイツ)7位 リース・ネルソン(カナダ)8位 ライカ・ベンチュラ(ブラジル) 左から伊藤、コベル、松本の順 ©Jason Halayko/X Games 女子ストリート 優勝 クロエ・コベル(オーストラリア)/ 90.00pt準優勝 伊藤 美優(日本)/ 81.00pt3位 松本 雪聖(日本)/ 77.00pt4位 吉沢 恋(日本)/ 74.00pt5位 中山 楓奈(日本)6位 織田 夢海(日本)7位 ペイジ・ヘイン(アメリカ合衆国)8位 西矢 椛(日本) 左からクーリー、サンチェス、シャーの順 ©Jason Halayko/X Games 男子バート優勝 ギー・クーリー(ブラジル)/ 90.66pt準優勝 JD・サンチェス(アメリカ合衆国)/ 88.33pt3位 トム・シャー(アメリカ合衆国)/ 83.00pt 4位 猪又 湊哉(日本)/ 51.66pt5位 テイト・カリュー(アメリカ合衆国)6位 河上 恵蒔(日本)7位 エリオット・スローン(アメリカ合衆国)8位 芝田 モト(日本) 左から芝田、クーリー、猪又の順 ©Jason Halayko/X Games 男子バート・ベストトリック優勝 ギー・クーリー / ブラジル準優勝 芝田 モト / 日本3位 猪又 湊哉 / 日本 4位 エリオット・スローン / アメリカ合衆国5位 河上 恵蒔 / 日本6位 JD・サンチェス / アメリカ合衆国7位 トム・シャー / アメリカ合衆国 左から四十住、トルー、草木の順 ©Jason Halayko/X Games 女子パーク優勝 アリサ・トルー(オーストラリア)/ 93.33pt準優勝 四十住 さくら(日本)/ 87.66pt3位 草木 ひなの(日本)/ 85.66pt4位 開 心那(日本)/ 83.66pt5位 スカイ・ブラウン(イギリス)6位 ブライス・ウェットスタイン(アメリカ合衆国)7位 リリー・エリックソン(アメリカ合衆国)8位 藤井 雪凛(日本) 左からカン、根附の順 ©Jason Halayko/X Games 男子ストリート優勝 根附 海龍(日本)/ 92.33pt準優勝 ジュニ・カン(韓国)/ 91.66pt3位 小野寺 吟雲(日本)/ 90.66pt4位 ジェイク・イラーディ(アメリカ合衆国)/ 88.66pt5位 ジュリアン・アギラルディ(アメリカ合衆国)/ 86.00pt6位 佐々木 音憧(日本)/ 84.33pt7位 池 慧野巨(日本)8位 ケルビン・ホフラー(ブラジル)9位 池田 大暉(日本)10位 ブレイデン・ホーバン(アメリカ合衆国)11位 コルダノ・ラッセル(カナダ)12位 キーラン・ウーリー(オーストラリア) 左からパルマー、シャー、カリューの順 ©Jason Halayko/X Games 男子パーク優勝 トム・シャー(アメリカ合衆国)/ 90.33pt準優勝 キーガン・パルマー(オーストラリア)/ 85.33pt3位 テイト・カリュー(アメリカ合衆国)/ 84.00pt4位 ペドロ・バロス(ブラジル)/ 79.66pt5位 ギャビン・ボドガー(アメリカ合衆国)6位 キーラン・ウーリー(オーストラリア)7位 トレイ・ウッド(アメリカ合衆国)8位 永原 悠路(日本) 大会概要 ⼤会名称 : X Games Osaka 2025開催期間 : 2025年6月20日(金)~22日(日) – 3日間 (一般開場は21~22日の2日間)-※詳細は公式HPをご覧ください。※金曜は公式練習日のため関係者・招待客・取材媒体のみ。一般入場は土曜と日曜の2日間です。 会場:京セラドーム大阪(KYOCERA DOME OSAKA) 主催: X Games Osaka 2025 組織委員会、株式会社 XGJ、日本テレビ放送網株式会社、株式会社ライブエグザム、株式会社イープラス、株式会社CB、株式会社グッドスマイルカンパニー、読売テレビ放送株式会社 主管: 大阪府、大阪市 後援: 一般社団法人ワールドスケートジャパン、一般社団法人日本スケートボーディング連盟、一般社団法人全日本フリースタイルBMX連盟、一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会、一般社団法人TEAM JAPAN MX PROJECT、FM802 / FM COCOLO、読売新聞社 協賛: Monster Energy、INSTYLE GROUP、ムラサキスポーツ、モスフードサービス、日本郵政、SANDISK、バンテリン、Mizkan NEW酢SHOT 協力: 公益財団法人JKA、モトクロスインターナショナル、株式会社JTB、シミズオクト、Skatelite by 井上スダレ株式会社、Yogibo、TOYO TIRE株式会社、TryHard JAPAN、くれおーる、ラーメンまこと屋
-
bmx京セラドーム大阪が歓喜と涙に包まれた日本のBMX界の歴史に残る快挙の数々【X Games Osaka 2025】BMX各種目まとめレポート2025.06.23日本国内では4回目となったX Games。今回千葉から大阪へと会場を移し関西初上陸となった「X Games Osaka 2025」が京セラドーム大阪にて2025年6月20日(金)~22日(日)に開催され、BMX競技からはフリースタイルの「パーク」、「パーク・ベストトリック」、「ストリート」そして「フラットランド」の4種目により世界最高峰のバトルが繰り広げられた。また「パーク」では中村輪夢選手が、「フラットランド」では内野洋平選手が悲願の初X Games金メダルを獲得し、後世代々に語り継がれるような日本のBMX界の歴史を塗り替えるほどの記念すべき快挙となり、日本のアクションスポーツシーンにとっても特別な大会となった。 今回の「X Games Osaka 2025」は、会場を大阪市の中心にある京セラドーム大阪に置いたことで関西地域の各方面からのアクセスも良く、屋内で天候に左右されない上に、かつドームという特性上全ての競技が見栄えするコース配置の環境から、観客は世界最高峰のトップアスリートのパフォーマンスを非日常的な雰囲気の中で観戦。終始大熱狂の中で大会は進行していった。 さらに今大会の各種目は「パーク・ベストトリック」と「フラットランド」を除いて、X Gamesは今年から新フォーマットを導入。これによってどの種目も一度に予選から決勝まで進められるスタイルに変わり、観客にも勝敗の行方が分かりやすくなる中で、まさにこれが「X Games」というような各ライダーたちがこの雰囲気の中だからこそ魅せられる異次元の大技の数々と、その節々にBMXが持つカルチャーがふんだんに表現された戦いが見られた。 そしてX Gamesのもう一つの魅力は、大会ごとにその国と土地柄を象徴した特徴的なセクションが用意されることだ。今回は関西で初開催ということから、パークコースでは都会のど真ん中をイメージしたコースに様々なセクションも用意され、一方でストリートのコースでは大阪の人気観光地の「道頓堀」をモチーフにしたレイアウトの中に大小様々なセクションが設置されるなど、この特徴な両コースにどのようにライダーたちが短い練習時間の中で順応しセクションをフル活用して観客に魅せるライディングするのかが注目された。 本記事では今大会各種目での注目選手と日本人選手の活躍をまとめた大会レポートを紹介。 今大会にて最初のBMX種目となった「パーク」では、中村輪夢が追い求めた悲願の初X Games金メダルを地元・関西の地で見事獲得! 中村輪夢 ©Jason Halayko/X Games 合計8名が出場したパーク種目はX Gamesの新フォーマットであるプレイオフを勝ち上がった4名が決勝で争う形に。プレイオフと同様に決勝でも45秒間のランを2本走行しその中で最も良い得点のランが採用されるベストランフォーマットでの戦いとなった。 今回見事悲願の金メダルを獲得したのは、日本人唯一の招待選手として参加した中村輪夢。2019年の「X Games Minneapolis 2019」で銀メダルを獲得して以来、5年もの間X Gamesメダルを手にできていなかった中で、昨年の「X Games Chiba 2024」では銀メダルを獲得。世界王者の経験もあり様々な世界大会で強さを見せている彼だが、キャリアを通して見るとなかなかX Gamesのメダル獲得には縁がなかった。その中で今回地元関西で開催されたこのX Games。ここでの金メダル獲得に誰よりも強い思いを持っていた彼は、決勝ラン1本目で「バックフリップ・バースピン to バーバック」、「フレア・ノーハンダー」、クオーターでの「テールウィップキャッチ to テールウィップ」などの高難度かつオリジナリティの高い唯一無二のトリックをハイエアーとスタイルを織り交ぜながら披露。地元の応援を力に変えたフルメイクのランで87.00ptをマークした。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) ラン2本目ではアップデートできずも1本目の得点を守り切り、中村自身悲願のX Games金メダルを獲得。これはフラットランド種目を除くBMX競技の中で日本人初の金メダル獲得の快挙であり、大会後は仲間たちが涙を浮かべながら中村に駆け寄り、今までの彼の努力が実ったこの日本のBMXシーンの歴史的な功績を称える姿がとても印象的だった。 中村輪夢 ©Jason Halayko/X Games 銀メダルは「X Games Ventura 2024」の金メダリストで、昨年の「X Games Chiba 2024」では銅メダルを獲得したアメリカ合衆国のマーカス・クリストファー。スピーディーのライディングの中で繰り出す豪快なトリックが特徴な彼は、自身の得意技でもある「トリプルダウンサイドテールウィップ」をはじめ、「720ダウンサイドテールウィップ」、さらにユニークなトランスファーでの「ノーハンド」など次々にメイク。ラストトリックには「フレア・ターンダウン」を決め切り、ラン1本目で84.66ptをマークした。ラン2本目では得点を伸ばせずも表彰台の座を守り切り、昨年の銅メダルを上回る銀メダルを獲得した。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) 銅メダルには昨年のパリオリンピックの銅メダリストでもあるフランスのアンソニー・ジャンジャン。パワフルなライディングの中に組み込まれた豪快な回転技を特徴する彼は、今回も「720バースピン」をはじめ、「フレア・ダブルテールウィップ 」、ラストトリックには「アリウープ540・フレア」もメイクするなど安定したライディングを見せて、ラン1本目で82.00ptをマーク。中村の高得点獲得によるプレッシャーからか各選手が苦戦を強いられたラン2本目ではジャンジャンも得点を伸ばすことはできなかったが3位の座を保持し、自身初のX Gamesメダルを銅メダルとした。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) パーク・ベストトリックはもはやビデオゲームの世界。異次元のトリックを時間内に見事にメイクしたライアン・ウィリアムスが金メダルを獲得! ライアン・ウィリアムス ©Jason Halayko/X Games 大会初日に開催された同競技のベストトリック。その前に行われた通常のラン種目である「パーク」とは違い、一発のトリックの難易度が競われるこの種目では観客全員が目を疑うほど、一般的には訳が分からないような異次元トリックが披露され、BMXフリースタイルのネクストレベルを感じさせる一戦となった。 今大会の競技フォーマットは20分のジャムセッションの中でのベストトリック採用方式で8名の招待選手が出場。本種目には日本で大人気のケビン・ペラザ(メキシコ)や、本種目だけの出場となった世界初のトリックを生み出し続けるライアン・ウィリアムス(オーストラリア)、さらに「ミスター・パーフェクト」の呼び名で知られるローガン・マーティン(オーストラリア)も参戦した。 以下は入賞者3名が魅せた特に印象に残ったベストトリックを紹介。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) まずは今回一の会場の盛り上がりを起こして金メダルを獲得した、ライアン・ウィリアムス(オーストラリア)のベストトリック。このトリックは「フロントフリップ・フレアテールウィップ」と言い、クオーターに向かって前回転するフロントフリップに180度回転しながら、テールウィップを決める超大技。これは通常のフレアと違いクオーターの飛び面に対して前回転を入れるところが肝となっており、これが異次元の難易度を生み出している。前回の「X Games Chiba 2024」では「ダブルバックフリップフェイキー」を決めきれずメダルをを逃した彼だったが今回は見事そのリベンジを達成。今回の金メダルによって自身9個目のX Games金メダル、そして合計11個目のX Gamesメダルを獲得した。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) そして本種目で銀メダルを獲得したのは残り5分のところでベストトリックをメイクしたローガン・マーティン(オーストラリア)。ボックスジャンプでメイクした「360バックフリップ・ダウンサイドテールウィップ to バースピン」だ。そもそも「360バックフリップ・ダウンサイドテールウィップ」の時点で超高難度な大技なのは当然なのだが、さらに着地直前にバースピンを加えてそのまま着地するというまさにミスターパーフェクトだからなせるトリックであることは間違いない。昨年の「X Games Chiba 2024」ではベストトリックに出場していなかったマーティン。日本の観客にとっても新鮮な画だったのではないだろうか。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) 最後は今大会最多の3種目に出場したケビン・ペラザ(メキシコ)がボックスジャンプでメイクした「フレアテールウィップフェイキー」。もちろん「フレアテールウィップ」自体が高難度トリックなのだが、それ以上にペラザが卓越しているのがフェイキーからの戻し。バックサイドの面にぴったり合わせるとスピードの付いたバイクを見事にコントロール。このあたりは彼がストリート種目でも強さを見せているのが納得できるグラウンドでの動きだった。 過去最高金メダル数を保持するレイノルズらを抑えてカレッジ・アダムスが金メダル獲得。そしてX Games史上最年少のBMX出場選手となったのは日本の早田颯助 祝福されるカレッジ・アダムス ©Jason Halayko/X Games 大会最終日に開催されたBMXストリートの決勝ではスケートボードストリート種目と同じ、階段や手すりなど街中の人工物を模したセクションが用意された「道頓堀」をモチーフにしたストリートのコースを使用。招待選手8名によりプレイオフにて45秒間のランを2本走行した後、ベストスコアを持つ上位4名が決勝に駒を進めて再度45秒間のランを2本走行した上でベストスコアが採用されるベストラン方式で争われた。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) 今回の金メダルは最終ランで大逆転を見せたカレッジ・アダムス(スペイン)。過去最高金メダル獲得数保持するギャレット・レイノルズなど強豪たちがひしめく中、ラン2本目では「ノーズウィリー to バースピン」、「180バースピン540バックラッシュ」や、「バースピン to マニュアル to バースピン to アイスピック・グラインド」のロングコンボ。そして「マニュアル to 180バースピン」などの技を決め91.33ptをマークすると一気にデボン・スマイリーを追い越し優勝。悲願の自身初のX Games金メダルを獲得した。優勝が決まった瞬間にはコース上で他のライダーたちからシャンパンシャワーならぬウォーターシャワーが行われ一緒に初の金メダル獲得を祝った。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) 銀メダルは昨年の「X Games Chiba 2024」でも銀メダルを獲得した、マニュアルを使ったトランジションから繰り出すトリックに定評のあるデボン・スマイリー(アメリカ合衆国)。今回もマニュアルを駆使した中に様々なレールやラインでのグラインドトリックを魅せる。特に特徴的だったのは様々なセクションに細かく入れてくる180をはじめとした回転技。逆方向に向かって回転することでバックサイドやセクションが見えにくくなるため難易度が増すが、安定したスピードを元にまとめ切ったフルメイクランで90.00ptをマークし、一時は暫定1位となったがアダムスに逆転を許し銀メダル獲得となった。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) 銅メダルはウェールズのジョーダン・ゴッドウィン。特にフロントペグを使ったグラインドトリックがスタイリッシュでかつハイレベルな彼は、コース内のセクションを多く使い、随所で魅せる「ターンダウン」や「トボガン」のスタイルが光っていた。最後はダブルペグのグラインドの難しい体勢から「360」を見せるなど終始スタイリッシュにランをまとめて87.66ptをマーク。自身2個目となるX Gamesメダルとして今回は銅メダルを獲得した。 View this post on Instagram A post shared by Sosuke Hayata (@sosuke_bmx23) そして最後に触れておきたいのはX GamesにおけるBMXの歴史に最年少出場者として名を残した早田颯助だ。今回は元々リザーバーとしての参加だったが、出場予定だった「X Games Chiba 2022」金メダリストであるルイス・ミルズ(オーストラリア)の欠場により出場が叶った。結果としては惜しくも望ましいかたちにはならなかったが世界最高峰のストリートライダーたちと肩を並べて同じ土俵で弱冠14歳の日本の若手が戦ったことは世界中の若手ライダーに希望を与えたことであろう。ここ最近はSimple Sessionといった国際大会にも出場している早田の今後の活躍にも注目していきたい。 X Games Osaka 2025に帰ってきたBMXフラットランド。最後まで分からない接戦の末、内野洋平が自身初のX Gamesメダルを金色に彩った! 内野洋平 ©Jason Halayko/X Games 大会最終日に開催されたBMXフラットランドの決勝では、招待選手9名により予選、準決勝を勝ち進んだ3名により争われ、7分間のジャムセッションの中で各選手が1回最大40秒間を持ち時間にベストルーティンを披露する形で複数回トライ。その中でのベストルーティンが採用されるベストトリック方式で争われた。なお日本からは内野洋平、佐々木元、片桐悠、早川起生の4名が出場。そして図らずも決勝は内野洋平、佐々木元、片桐悠の3名で日本人対決となった。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) 今回見事金メダルを獲得したのは、過去通算11度の世界タイトルを獲得し、日本のBMXフラットランドが世界最高峰であることを証明し続けているレジェンドであり、今もなおトップライダーとして強さを見せ続けている内野洋平。近年では優勝から遠のくなど辛酸を舐める経験をしてきた彼。今回は先月の「Spark ONE」で見せたトリックをアップデートして、バックスピンからのハーフバイクフリップからまたハーフバイクフリップそしてバックスピンで戻す高難度ルーティンを決めた。これまで「X Games Chiba」では2022年、2023年と出場してきたがメダル獲得は叶わなかった内野。彼の輝かしい世界タイトルの数々の中にX Gamesでのタイトルは無かったため、BMXフラットランドライダーにとっては誰もが手にしたいX Gamesでの金メダルを自身の地元である関西で獲得できたことへの喜びはひとしおだろう。なお現在42歳の内野の今回の金メダル獲得はX Games史上最年長記録に続く2番目の記録。何歳になっても強さを示し続ける彼の今後の活躍に注目したい。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) 銀メダルを獲得したのは内野洋平と同様に長年日本のBMXフラットランドシーンを牽引している佐々木元。彼も「X Games Chiba 2022」から3度目の出場となった今大会。しかし彼は4月の「マイナビ Japan Cup」から右腕を負傷し今大会に向けても十分な練習ができない中での参戦となった。予選、準決勝と勝ち進んでいく中で悲鳴を上げていた身体だったが、決勝では自身のフロントトリックをベースをしたシグネチャートリックも加えたルーティンを展開し見事決め切って見せた。なお今回の銀メダルは彼のX Gamesの成績としては2022年の銅メダルを超えて過去最高となった。 View this post on Instagram A post shared by X Games (@xgames) 銅メダルには「X Games Chiba 2023」金メダリストで、常に世界最先端を突き進むBMXフラットランド界をレベルを引き上げ続けているトップライダーの片桐悠。今大会でも予選と準決勝と異次元のルーティンを披露し、満を持して迎えた決勝ではなかなか自分の思うようにコンボをメイクできず苦戦を強いられた。バイクを縦に跨ぐペダル軸のツーフットのバックワーズから体勢を変えながら構成する難しいペダル軸でのルーティンにトライし、タイムオーバーギリギリまでメイクを目指したが今回は惜しくもメイクとはならず。しかし今回金メダルを獲得した内野とは師弟関係である片桐。大会後はお互いを称え合う様子も見られ、BMXのカルチャーの良さを感じられる一面だった。とはいえこのまま負けているままとも思えないのがこの片桐。今後のさらなる活躍に期待していきたい。 大会結果 左からクリストファー、中村、ジャンジャンの順©︎Jason Halayko/X Games BMXパーク優勝 中村 輪夢(日本)/ 87.00pt準優勝 マーカス・クリストファー(アメリカ合衆国)/ 84.66pt3位 アンソニー・ジャンジャン(フランス)/ 82.00pt4位 ローガン・マーティン(オーストラリア)/ 77.66pt5位 ホセ・トーレス(アルゼンチン)/ 74.66pt6位 ブライス・トライオン(アメリカ合衆国)/ 71.00pt7位 ダニエル・サンドバル(アメリカ合衆国)/ 70.00pt8位 ケビン・ペラザ(メキシコ)/ 63.00pt 左からマーティン、ウィリアムス、ペラザの順©︎Jason Halayko/X Games BMXパーク・ベストトリック優勝 ライアン・ウィリアムス / オーストラリア準優勝 ローガン・マーティン / オーストラリア3位 ケビン・ペラザ / メキシコ 4位 ダニエル・サンドバル / アメリカ合衆国5位 マイク・バーガ / カナダ6位 ジェレミー・マロット / アメリカ合衆国7位 ブライス・トライオン / アメリカ合衆国8位 アンソニー・ジャンジャン / フランス 左からスマイリー、アダムス、ゴッドウィンの順©︎Jason Halayko/X Games BMXストリート優勝 カレッジ・アダムス(スペイン)/ 91.33pt準優勝 デボン・スマイリー(アメリカ合衆国)/ 90.00pt3位 ジョーダン・ゴッドウィン(ウェールズ)/ 87.66pt 4位 ギャレット・レイノルズ(アメリカ合衆国)/ 87.00pt5位 ボイド・ヒルダー(オーストラリア)/ 83.33pt6位 ケビン・ペラザ(メキシコ)/ 80.66pt7位 フェリックス・プランゲンバーグ(ドイツ)/ 78.00pt8位 早田 颯助(日本)/ 56.66pt 左から佐々木、内野、片桐の順©︎Jason Halayko/X Games BMXフラットランド 優勝 内野 洋平(日本)準優勝 佐々木 元(日本)3位 片桐 悠(日本)4位 早川 起生(日本)5位 ヴィッキー・ゴメス(スペイン)6位 アレックス・ジュメリン(フランス)7位 マティアス・ダンドワ(フランス)8位 テリー・アダムス(アメリカ合衆国)9位 ジーン・ウィリアム・プレボースト(カナダ) 大会概要 ⼤会名称 : X Games Osaka 2025開催期間 : 2025年6月20日(金)~22日(日) – 3日間 (一般開場は21~22日の2日間)-※詳細は公式HPをご覧ください。※金曜は公式練習日のため関係者・招待客・取材媒体のみ。一般入場は土曜と日曜の2日間です。会場:京セラドーム大阪(KYOCERA DOME OSAKA)主催: X Games Osaka 2025 組織委員会、株式会社 XGJ、日本テレビ放送網株式会社、株式会社ライブエグザム、株式会社イープラス、株式会社CB、株式会社グッドスマイルカンパニー、読売テレビ放送株式会社主管: 大阪府、大阪市後援: 一般社団法人ワールドスケートジャパン、一般社団法人日本スケートボーディング連盟、一般社団法人全日本フリースタイルBMX連盟、一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会、一般社団法人TEAM JAPAN MX PROJECT、FM802 / FM COCOLO、読売新聞社協賛: Monster Energy、INSTYLE GROUP、ムラサキスポーツ、モスフードサービス、日本郵政、SANDISK、バンテリン、Mizkan NEW酢SHOT協力: 公益財団法人JKA、モトクロスインターナショナル、株式会社JTB、シミズオクト、Skatelite by 井上スダレ株式会社、Yogibo、TOYO TIRE株式会社、TryHard JAPAN、くれおーる、ラーメンまこと屋
-
dance【SHIROFES.10周年記念対談】ストリートダンスが紡ぐ弘前と世界、そして未来への街づくり2025.06.20はじめに 青森県にある弘前市(ひろさきし)をご存知だろうか。弘前の特徴として青森県南西部にあり日本で最初に市制を施行した都市の一つである。弘前藩の城下町として発展し、津軽地方の中心都市として弘前都市圏を形成し、青森県唯一の国立大学法人である弘前大学が設置されているほど青森を代表する中心地だ。 また、りんごの生産量は弘前市が全国一を誇り、弘前公園で開催される弘前さくらまつりや弘前城も全国的に知られており「お城とさくらとりんごのまち」のフレーズは古くから使われている。8月には、国の重要無形民俗文化財に指定されている「弘前ねぷたまつり」が開催され、例年100万人以上の人出があり、全国的に知名度のある夏祭りも開催されている情熱と伝統が色濃く残る地でもある。 その弘前で、近年急成長を遂げているイベントが今年も開催される。それが弘前城の城が由来の「SHIROFES.」だ。 「SHIROFES.」は、今年で10回目の開催を迎える。初期から内容を拡張し、現在は音楽、ダンス、そして様々なアートが融合した、まさに複合型の一大イベントへと成長を遂げている。観客の熱気、ダンサーのエネルギーとパワー、そして運営スタッフの情熱がエネルギーの塊となり、まさに「目覚めろ、個性。燃え上がれ、弘前。」というキャッチフレーズを体現するイベントとなっている。今回は、このSHIROFES.を支える弘前の櫻田市長と、イベントを牽引するオーガナイザーのNOBUOにその軌跡と現在のSHIROFES.がもたらす影響、そして街づくりについて話を訊いた。 SHIROFES.2025 - 本日はお忙しい中、貴重なお時間をいただきありがとうございます。早速ですが、昨年のSHIROFES.をご覧になられた感想を教えていただけますか? 櫻田市長: 昨年のファイナルは、まさにエネルギーの塊を体で感じ、圧倒されました。ブレイクダンスなど各大会の決勝戦では、ダンサーの方々が相手をリスペクトしながらも最高のパフォーマンスを繰り広げ、会場が一体となっていました。若い人たちが市民会館を埋め尽くしている姿を見て「これが今の時代の新しい、全てを融合した一つの文化になっているのだな」というのが私の率直な感想です。SHIROFES.は単なるダンスイベントではなく、弘前が世界と繋がる象徴となっており、若者たちが自己表現できるかけがえのない舞台になっていると強く感じました。 SHIROFES.2024 1on1バトルの様子 - 昨年は予期せぬアクシデントがあったかと思いますが、無事に終えられた時の感想を教えてください。 NOBUO: そうですね、コロナ禍に入ってオンライン開催や無観客開催もありましたが、昨年ようやく市民会館がある弘前公園の方で実施することができました。そこに災害レベルの雨が降ってきたのですが、奇跡的に市民会館を使わせていただくことができ、屋内に急遽残りのプログラムを移動することができました。通常なら中止になっていただろう状況で、関わってくれるスタッフや日本を代表するダンサーの方々が裏で同じように動いてくれて、結果的に最高の盛り上がりを見せることができました。コロナ禍を経て、トラブルに見舞われながらも開催できたことが、自分としては非常に大きかったと感じています。オンラインからリアルな対面開催への移行、そしてトラブルを乗り越えたからこそ生まれた熱量が、ダンスイベントならではの得られた経験だったと感じています。 SHIROFES.2024 ゲリラ豪雨に見舞われ会場は一時騒然となる - 櫻田市長も現場にいらっしゃったと思いますが、当時の状況をみてどのように感じましたか? 櫻田市長: 私も2日間ほど会場で観覧をさせていただいていたのですが、豪雨になった時は大変な状況だと感じました。しかし、コロナ禍でも中止せずオンライン開催で世界と繋がるきっかけを作った彼らの「常に前を見続けて進む、止めることはしない」という強い思いが、様々な人たちの力を借りながらイベントとして成立しているのだと実感することができました。市民会館への急な変更にもかかわらず、まるで最初からそこで予定されていたかのような完成度の高いステージになっていました。これは市民が自ら作り上げてきたイベントの象徴であり、これからも市民、アーティスト、スタッフが交流しながら新しい文化を作っていくイベントになると感動しました。 SHIROFES.の成長と街づくりの影響 - SHIROFES.は全国的に見てもその規模や招集されるダンサーのレベル、そして幅広い世代が集まる点が他に類を見ないイベントだと感じます。この10年間の努力が積み重なってのことだと思いますが、特に成長する上で大きなきっかけになったことがあれば教えてください。 櫻田市長: 最初は弘前城の天守の石垣工事をきっかけにイベントが始まったのですが、私が思うに、急成長の大きなきっかけはコロナ禍でのオンライン開催だったと思います。あの時、「どうすれば自分たちの取り組みを止めることなく続けられるか」と真正面から向き合い、オンライン開催に踏み切ったことが、通常開催を重ねるよりもさらに飛躍的な成長を遂げたのではないかと感じています。困難があればあるほどそれを乗り越えていく力を持っているからこそ、実際に乗り越えていける。これが人としての成長、そして市民を巻き込んだイベントとしての成長に繋がっていると思います。 コロナ禍でのオンライン開催時の櫻田市長とNOBUO NOBUO: 弘前市の方々には本当に数え切れないほど多くの部分で協力していただいています。SHIROFES.が生まれて10年になりますが、その前から僕個人としては様々なイベントを開催していましたし、SHIROFES.の10年間も並行して様々なイベントや事業を行ってきました。そうしたなかで実感するのは、SHIROFES.以外の他のイベントに足を運んでくださる方が凄く増えたこと、そして初めて会うお店のスタッフさんから「SHIROFES.楽しみにしています!」と声をかけていただけることです。“楽しみにしてもらえる”という点で地元の方からも理解が得られていることが、協力してもらっていると凄く感じる部分ですね。僕がダンススタジオを始めた18年ほど前は、ダンスに対する理解度や認知度が低く、ダンサーや子供たちも今ほど市民権を得ていなかった中で、皆がそれぞれの立場でダンスシーンを盛り上げようとしてきた結果、今ではダンス関係者のみならず、地元の方からの応援も多く感じられるようになりました。SHIROFES.がそれをさらに繋げてくれたという手応えがとてもあります。 - 櫻田市長は、SHIROFES.が街に広まり、良い影響をもたらしていると実感されていますか? 櫻田市長: はい、そうですね。SHIROFES.は、若い人が集まるイメージでしたが、会場に行くとご高齢の方や私と同年代のご夫婦まで来られていました。地域の方々がSHIROFES.を認知し、若い人たちが集まる姿を見に来る、そうした「街づくり」に近いところまで来ていると思います。先日も、Shigekixさんをはじめとした世界レベルのダンサーの方々が十名ほど市役所を表敬訪問してくださいました。その際、私の目の前でパフォーマンスをしてくれたんです。こんな贅沢な市長はいないなと思いましたし、これは地域に対する大きな貢献であり、市民がどう受け止め、どう育てていくかが試されている、これこそが街づくりそのものであると感じました。 弘前市役所を表見訪問する世界トップクラスのBBOY・BGIRLたち - 今年は近隣の宿泊施設がすでに満室になっているほど、盛り上がりをみせていると伺いました。まさに街づくりですね。NOBUOさん、昨年の反響が大きいのでしょうか? NOBUO: そうですね、今年の大会はエントリー数がすでにものすごい速さで昨年の記録を超えていて、定員に達している大会もあります。15歳以下の子供たちの参加人数だけで400人を超えていて、そのご家族もいらっしゃると考えると400家族くらい。大会参加者(出演者)全体ですでに1,300人を超えている状態です。そして、全国だけでなく、昨年よりもさらに海外のダンサーのエントリーが増えているんです。さらに驚いたのは、エントリーをせずにただ「見に行きます」と言ってイタリアから来られる方がいることです。直接DMをもらい、おすすめのホテルや食事、SHIROFES.の楽しみ方、弘前での5日間の移動手段などを尋ねられました。見に来るためだけにわざわざ海外から来られる方がいるというのは、僕の知る限りはこれまでなかったので、とても新鮮でしたし昨年の反響を感じますね。 SHIROFES.2024 市民会館の様子 海外から5日間も弘前に滞在してイベントを見に来てくれるというのは、ある意味本当に一線を越えた、僕らの中では「ダンスの聖地」になったという感覚があります。そして今年からは、オンライン開催時に繋がったベトナムのダンサーから要望を受けたSHIROFES.の予選大会をベトナムで開催することができました。そこで優勝した大人と中学生の男の子が、初めてパスポートを取って弘前に来るんです。ベトナムの大会もすごい盛り上がりで、台湾の方々も見に来ていて「来年はぜひ台湾でもやってほしい」と言われました。弘前の地元企業の方々も、海外での観光PRや、弘前りんごジュースを参加者に配るといった形で協力してくださっています。アジア圏では弘前は認知度が皆無に等しいと思うのですが、「SHIROFES.に行きたい!」と言っている人がたくさんいて、弘前を訪れてくれる機会になればと思います。弘前からもベトナムへ連れて行った子供たちがいるのですが、そこでベトナムの子供たちから「SHIROFES.はすごい!」と言われたり、見知らぬ土地でSHIROFES.を目標にダンスを頑張っているダンサーたちと触れ合うことができ、良い意味でカルチャーショックを受けていました。コロナ禍を経て海外の人たちと繋がったことで、日本から視る海外、弘前から視る海外といった視点で考えるようになり、文化交流や経済的なPR、おもてなしの部分で弘前らしさを出せるのではないかと考えるようになりました。 SHIROFES. ベトナム予選大会の様子 弘前のダンス文化を支える「練習場所」誕生秘話 - ダンスは言葉も道具もいらないツールとして、国際交流の文化として地域に根付き発展しているんですね。櫻田市長はストリートダンスに対してSHIROFES.以前から関心をお持ちでしたか? 櫻田市長: ええ、実は弘前市役所の隣にある市立観光館の建物で、もう20年以上前から夜になるとカセットデッキを持ってきて音楽をかけ、ダンスをする若者をたくさん見てきました。観光館の管理者はその様子を危険だと考えていましたが、私は当時弘前市長の秘書をしていたのですが、市長に対し「彼らは自分たちでペットボトルを持ってきて、ゴミも残さずきれいに片付けている。純粋にダンスをしている。この人たちにスポットライトを当てられないか」と相談したことがありました。 市立観光館のガラス張りは現在も貴重な練習場所に その後、私の職員時代のことですが、弘前の駅前にある複合施設「HIRORO」のフリースペースに若者が集まってダンスをしているという話を聞き、鏡を設置することを提案しました。市役所の食堂の建て替えで残っていた昭和40年代の鏡を貼り、足りない分は市役所の方で整備をして全体で3、4枚貼ったところ、若者がただ集まるだけでなく、そこでダンスをすることで治安が良くなったんです。ダンスをしていた人たちをサポートできた経験があったので、SHIROFES.が始まったときも「あの時、あの場所で踊っていた人たちが、弘前で成長をし、いろいろと挑戦をしているんだな」と思い、職員として応援し、市長になってからもその想いは継続しています。 HIROROの練習広場親子共に安心して自由に練習ができ交流場にも NOBUO: まさにその観光館でカセットデッキを持って練習していた第一世代が僕らなんですよ。櫻田市長がおっしゃる20数年前というのはまさに僕らの時代です。当時から、弘前には「中下(ナカシタ)」というダンサーの聖地と呼ばれる練習場所があったのですが、上手い人達が沢山いて僕は大学に入ってからダンスを始めたので、そこに行くのが怖くて(笑)。大学から自転車で行ける距離にあった観光館がとても良い場所だったので、ダンスを始めた頃は夜になると毎日行っていました。ライトアップされると光の加減で鏡のように映る場所があってちょうど良かったんですよね。HIROROの鏡の設置についてですが、この動きに関してはおそらく日本で一番最初の試みだったと思います。弘前ではデパートのフロアに鏡を設置して無料で練習できる場所を提供していて、今ではその経緯を知らない子供たちや、僕自身の子供でさえ、学校終わりにスクールからHIROROまで行って練習しています。複合施設のフリースペースで、親としても安全な場所なので、今では完全に子供たちにとってのダンスの聖地になっています。冬でも練習できるこうした場所はなかなかありません。多くの自治体の方がSHIROFES.を見に来る際にイベントだけでなく、そうした普段の練習環境や流れを追って視察されます。この鏡の経緯を聞かれると10年以上前の話なので、ダンスがオリンピック競技になるという話もない時代にすでに自然とできていたことに驚かれます。こうした環境が整っていたことが、若い子たちが伸びている要因だと強く感じています。SHIROFES.に限らず、この街には恵まれたダンスの環境がかなり早い段階からあったのだなと改めて思いました。 カセットデッキを片手に練習をしていた当時の仲間たち - 櫻田市長が当時、危険視されがちな若者の集まりを純粋にダンスに打ち込む姿として捉え応援しようと思われたのは、行政管理視点としては真逆のように感じたのですが何かきっかけがあったのでしょうか? 櫻田市長: 当時、私の仕事が忙しく夜中に残業して帰る時も、彼らはひたすらカセットデッキで音楽をかけて踊っていました。冬の寒い中でも毎日見ていたので「この人たちにコーヒーでも差し入れしようかな」と思うほどでした。ある時「大丈夫?寒くない?」と、声をかけたら「大丈夫です。ダンスの練習がしたいんです!」と元気いっぱいに答えてくれたことがすごく印象に残っています。その時に、見方を変えることによって「この若い人たちは何をしたいのか」が分かったんです。若い自分も何か挑戦したかった想いと重なり、少しでもサポートできないかと考えるようになりました。怪しいことをやっているという見方ではなく、何をしたいのかが分かると、自分たちがやりたいことを実現するためにはルールを守るといった、人としての当然のところが活きてくるんです。してはいけないとだけ言うのではなく、「一緒にこの地域で成長していこう」と感じたので、その当時からダンスが好きで踊っている人たちに何かしらサポートできないかと思っていました。それが鏡の設置となり、今に繋がっています。 SHIROFES.2024 優勝者を讃える櫻田市長 SHIROFES.が持つ魅力と未来への展望 - ストリートダンスやSHIROFES.の魅力について、改めてお伺いできますか? 櫻田市長: ダンスを通して自分の想いを表現していく。これはリズム感、身体的な筋力、柔軟さなど様々なものが関わってきます。自分の持つ能力の強い面、良い面を伸ばし、それが世界で戦う場に繋がっていることが素晴らしいと思います。ダンスを通して様々な人が関わり、自分は踊れなくても見ることで楽しめます。昨年は台湾の小さな子供が応援するためにSHIROFES.を訪れたという話も聞きました。このようにダンスを通して交流人口や関係人口が増えています。私は職員時代に観光を担当していましたが、現在のSHIROFES.はまさに観光誘致の世界であり、宿泊施設が満室になっている状況です。これは弘前では“さくらまつり”や“ねぷたまつり”くらいしかありません。観光誘致のみならず、文化の交流によって新しい経済活動が生まれていると感じており、これからの地域活性化に繋がると確信しています。 - ストリートダンスはジャンルが様々で、SHIROFES.はバトルコンテンツが多いと思います。特にダンスバトルは分かりにくい側面もあると思いますが、櫻田市長は率直に「楽しめるもの」だと感じますか? 櫻田市長: そうですね。率直にお答えすると・・「よく分かりません」。 一同(笑) SHIROFES.2024 クルーバトルの様子 櫻田市長: よく分からないんですけど「何かがすごいんだな」ということは周りの観客の方々の反応で感じます。私自身、どこがすごいのかはよく分かっていないかもしれませんが、昨年の会場の一体感やダンサーの方々がお互いをリスペクトし頂上を目指しハイレベルな戦いをしていることはわかりましたし、心が震える場面も多くありました。なので、私のような方がいらしても大丈夫です。わかっていなくても一緒になってこの空気感を楽しむということをすれば、新しい楽しみ方ができるかと思います。NOBUO: 僕としては、大会としてダンスバトルを行っているのですが、一方でダンスバトルだけじゃないダンスの楽しみ方を知ってもらいたいというのも正直あります。ダンスは音楽が軸であり、ヒップホップなどの洋楽だけでなく様々な音楽があり、地元の伝統芸能が入ると、他の地域から訪れたダンサーも「津軽三味線を生で初めて見た」と新しい発見をしてくれます。ダンスバトルは一つの「フック」だと思っていて、バトルを軸に弘前に来ようと思ってもらえる大会にしていくのが僕らの役目だと考えています。昨年のイベントが終わった際には、多くの地元の方々から「SHIROFES.のステージに立つのが夢なんです」と言っていただき、今年は地元市民のパフォーマンス時間を増やしました。ダンスを軸に始まったイベントかもしれませんが、ダンスバトルがきっかけで市外から人が訪れ、地元で様々な音楽や伝統芸能をやっている人たちもSHIROFES.の同じステージに立ちたいと思ってくれる。ダンスバトルも大事にしつつ、様々な音楽、ダンス、アート、伝統芸能が複合的に混ざることで生まれる地元密着型の空気感を大事にしていきたいと思っています。 SHIROFES.2024 地元アーティストによる津軽三味線の演奏 - 弘前市を代表する祭りと言っても過言ではない程に成長したSHIROFES.を、市としてはどのように捉えていますか? 櫻田市長: そうですね、SHIROFES.10年、あっという間でした。市民の皆さんがこのイベントを認知し、さらに楽しみにしてきている、市民の成長が大きな効果を与えてくれていると思います。ダンス、音楽、アート、地元の伝統芸能を含め、これらが総合的に地域と繋がり、弘前とSHIROFES.が成長を遂げてきています。これは若い人たちが弘前から世界へ羽ばたく大きなきっかけになっていると思います。夢を描き、自らの能力に挑戦し、世界で戦うんだという自信を市民の皆さんに与えてくれているのはこのSHIROFES.です。弘前は桜とりんごの街ですが、ダンスの街として大きく打ち出していける集客力がある。国外から人々が訪れ、世界で予選会を開きたいという声も出てきている。その中心が弘前だということは、ダンスの世界では弘前が「聖地」になりうるのではないかと感じています。これを市もしっかりと支え、様々な意味で協調していくことがこれからの地域づくりに繋がっていくと思っています。 SHIROFES.2024 野外ステージの様子 - 今後に向けて、どのような展望をお持ちですか? NOBUO: 一つひとつのコンテンツはこれからもレベルが上がっていくだろうと思います。僕自身は考える側ですが、実際に作るのは現場に立つアーティストやダンサーになってきているので、そこはどんどん伸びていくだろうと。その中で、僕らが弘前でやっていることが、他の地域でも同じようにできるのかという問いには、他の地域のオーガナイザーや海外のダンサーともっと繋がっていきたいという想いがあります。自分がやっているイベントが一番良い、と言いたいわけではなく、もっと他の地域との交流、そして弘前でダンスをやっている子供たちが地元にいながら外の地域の人たちと交流できる環境作りをしていきたいです。それがベトナム開催のきっかけにもなっていますし、海外で予選大会をやって、そこに地元の子供たちも連れて行ってパフォーマンスする機会を作るなど、もっとできることがたくさんあると感じています。 SHIROFES.2024 アクセス良好な弘前公園内で開催 日本では「決勝大会と言えば東京」といった主要都市にメインコンテンツが集中しがちですが、東南アジアなど他の地域にも広げることで、地方にいる子供たちが経験の格差を感じずに済むようにしたい。弘前だけで頑張るのではなく、全国の地方で頑張っているオーガナイザーと繋がって新しいムーブメントを作っていきたい。ベトナムをはじめ、今後はインドでの開催も考えています。僕自身はSHIROFES.を誰かに継いでほしいとは正直全く思っていません。若い世代の子たちが刺激を受け「弘前でイベントを作りたい!」と自主的に思うような環境を作りたいです。今あるものを育てるというよりは、新しいことができるようにするために、新しい文化や他の文化を持つ人たちとの交流をどんどんやっていかないと、結局何も感じないまま高校を卒業し、地元を出ていってしまうという地方の課題を解決したいです。ダンスシーンがどうこうという次元の話ではなく、僕らが僕らの立場で何を後世に残せるか、どういうことができるかが、下の子供たちやこれからの街に大きく影響すると感じています。 SHIROFES.2024 地元の学生もステージでパフォーマンスを披露 おわりに - 最後に、今年のSHIROFES.に来場される方や読者の皆様にメッセージをお願いします。 櫻田市長: このSHIROFES.は、ストリートダンスが単なるパフォーマンスではなく、その人の生き方そのもの、自分を表現する自由な手段であるということをダンスで表現していると思います。地元の子供たちも超一流の方々のダンスを見て大きな刺激を受けている、そのようなイベントに成長してきました。初開催から10年が経ちますが、市民の皆さんと一緒に作り上げてきたこのSHIROFES.というイベント、国内外から多くの皆さんにレベルの高いパフォーマンスダンスをぜひ見ていただき、そして文化としての祭典だと認識してもらいたいと思います。若者や地域の方々、さらには世界に挑戦する方々が一体となって作り上げるイベントですので、ぜひ多くの方々にお越しいただければと思います。 弘前城を舞台に開催され、まさに日本の複合型ダンスフェスの象徴とも言えるイベントに成長 NOBUO: そうですね、まず僕は弘前市で地元行政と連携を取りつつ10年間このイベントを開催してこれたことに関して、“恵まれているな”ととても思います。それを感じているのは僕自身だけでなく、「ダンスでここまでのものができるの?」という全国の関係者からのお声も多くいただきます。夢を与えてくれる街なのかなとすごく思いますね。だからこそ「どうやってやってるの?」と皆が思うところで、それは単純に「恵まれている」の一言に尽きるのかなと思います。どの地域でもできることかもしれませんが、やっぱりこれだけのことは弘前じゃないとできないよな、と自分自身すごく感じています。弘前だからこそこういうことができている、こういう相談もできる、という理解も少しずつ広がってきていると感じます。なので、SHIROFES.に遊びに来る人たちには、イベント自体を作っている人たちの熱量や、街全体の魅力も、ぜひ来ていただいた時に感じてもらえたら嬉しいです。 - 弘前はグルメも魅力的ですよね。ぜひ読者の方へおすすめグルメを教えてください。 NOBUO: 弘前の名物と言えばアップルパイですね! 櫻田市長: そうですね。また、弘前はイタリアンもフレンチも美味しいです。実はお寿司もびっくりするくらい新鮮なものが食べられるのでとっても美味しいですよ。 - 食も和洋折衷で楽しめるんですね!歴史も深く、食も文化も幅広く楽しめる弘前は観光としても非常に魅力的な地域ですね。本日は大変貴重なお話をありがとうございました。 プロフィール 青森県・弘前市長 櫻田 宏弘前大学人文学部経済学科卒業 略歴昭和58年4月 弘前市役所(福祉事務所保護課)採用昭和62年4月 総務部人事課 主事平成6年4月 市長公室企画課 主事平成8年4月 市長公室企画課 企画担当主査平成10年4月 企画部企画課男女共同参画室 男女共同参画担当主査平成11年4月 企画部秘書課秘書係 係長平成16年4月 企画部秘書課 課長補佐平成18年8月 商工観光部観光物産課 課長補佐平成23年4月 商工観光部観光局観光物産課 参事平成24年4月 商工観光部観光局観光物産課 課長平成25年4月 市民文化スポーツ部市民協働政策課 課長平成26年4月 経営戦略部 理事平成27年4月 観光振興部 部長平成30年4月16日 弘前市長に就任 NOBUO岩手県出身。弘前大学ストリートダンスサークルA.C.T.に所属し、ダンスを始める。大学院修了後、2008年にダンススタジオ「FUNKY STADIUM」をオープン。2012年、弘前市で芸術舞踊に関する活動を発展させるため、「ひろさき芸術舞踊実行委員会」を設立。2016年、弘前城本丸にて大規模野外フェスティバルSHIROFES.を開催。2021年、国が主催する「スポーツ文化ツーリズムアワード2021」で SHIROFES.が国内最高賞「スポーツ文化ツーリズム賞」を受賞。自身もダンサーとして活動し続け、更には育成などにも力を注いでいる。ダンススタジオ事業・イベント事業、レッドブルジャパン(株)のダンスコンテンツプロジェクトディレクターも務める。2023年10月より弘前大学大学院博士課程に進学。「カルチャーに対する熱量が及ぼす影響について」をテーマに研究も行っている。